
乳腺外科

乳腺外科
2026年2月から初診の方もWEB予約が可能となります。ただし、初診の方は今まで通りご予約なしでも診療いたします。
2025年4月から乳腺外科の担当医師が変更となります。
水曜日午前 天野院長→平方智子先生となります。
甲状腺科については水曜日休診となりますのでご注意ください。
当面の間、松谷彬子先生の診察日は初診の方は16:30受付終了となります。
午後の診察の方は込み具合によっては検査結果のお伝えも後日とさせていただきます。
16時過ぎのご来院は検査結果のお伝えは後日になる可能性が高いです。
患者様にはご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。
乳腺・甲状腺科の二人体制時には「院長希望」とおっしゃってください。
乳腺外科混雑時及び受付終了間際は、検査結果のご説明は後日(約1週間後)になることがございます。その際は、再診料が発生いたしますのでご了承ください。
初診の方は混雑時は診察は行いますが、検査は後日予約とさせていただくことがございますのでご了承ください。

乳がん患者様は毎年増加して、今では日本の女性が生涯を通じて、罹るがんの中で最も多いものとなったのは皆様ご存知のことと思います。そして、乳房の検診が重要であることは言うまでもありません。日本ではこれまで欧米のマンモグラフィ検診の実績を借用して、乳腺ドックにはマンモグラフィと触診が大切という理念のもとに検診を施行し、一定の評価を得てきました。しかし、検診での見落としという悲しい例も時に見られ、住民検診が100%の正診率でないことも明らかになりました。つまり検診を受けていれば万全ということはなく、質の高い検診を受けることが大切であるということが判りました。
そこで、日本独自の質の高い検診法を確立するために、乳房に症状がない40歳代の女性参加者72,998名を募り、マンモグラフィに超音波検査を併用する乳房検診システムを企画し、この方法が従来のマンモグラフィ単独の検診と比較して優れているかどうかを検証する研究を行いました(J-START)。その結果、マンモグラフィに超音波検査を併用したほうが、がんの検出率が増加し、また早期乳がんの発見割合が多いという結果が得られました。すなわち、マンモグラフィだけでは見落とされていたがんを、超音波を併用することで拾い上げることを科学的に証明しました(Lancet 2016; 387:341-48)。
一方、最近たくさんの乳がんが発見されるようになると、マンモグラフィや超音波検査をすり抜けて、MRIでなければ発見できない乳がんが知られるようになりました。乳房のMRIが既知病変の広がり診断だけではなく、多発病変の発見などにも有用であることが認められるようになりました。すでに米国や欧州のガイドラインでは遺伝性あるいは家族性乳がんのスクリーニングにMRIが勧められるようになっています(Lancet 2011; 19:1804-11)。このような最新の研究結果を踏まえ、新都心むさしのクリニックでは「見落としのない乳腺ドック」を開設理念の一つとして掲げ、できるだけ早期のうちに乳がんを発見することを目標にしています。
具体的には、3つの検査、マンモグラフィ、超音波検査、MRI検査の最新の機器を備え、診察やマンモグラフィの読影は読影資格AS認定の経験豊富な医師が行っています。さらに検査の手順も大切で、まずマンモグラフィを先に撮影し、その読影結果を踏まえて、超音波検査を行うという方式をとっています。この検診方法は最も効率がよく、見落としの少ない方法として学会でも知られておりますが、人的資源や検査機器の面から、どの施設でも可能というわけにはゆきませんでした。当院では、そのような効率よく、見落としの少ない方法で検診を行っています。マンモグラフィの被ばくに関しても注意が必要で、慎重な判断のもとに施行しています。
日本乳がん検診学会の乳がん発症ハイリスクグループに対する乳房MRIスクリーニングに関するガイドラインに準拠して、当院でも乳房MRI検査を行っています。
乳腺疾患の症状は自分で見て触って気付くこともよくあります。下記のような症状、項目に該当する方はご相談ください。
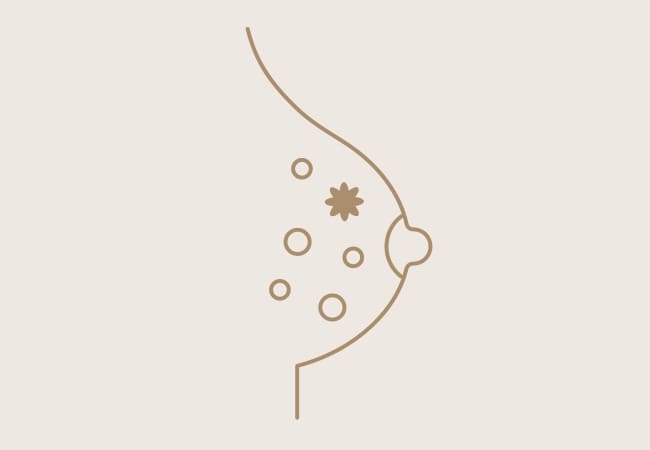
乳がん
乳がんは幅広い世代の女性が発症します。
ぜひ入浴や着替えの際に自分の乳房を見たり触ったりして確認してください。セルフチェックに加え、定期的な乳がん検診を受けて早期発見につなげましょう。
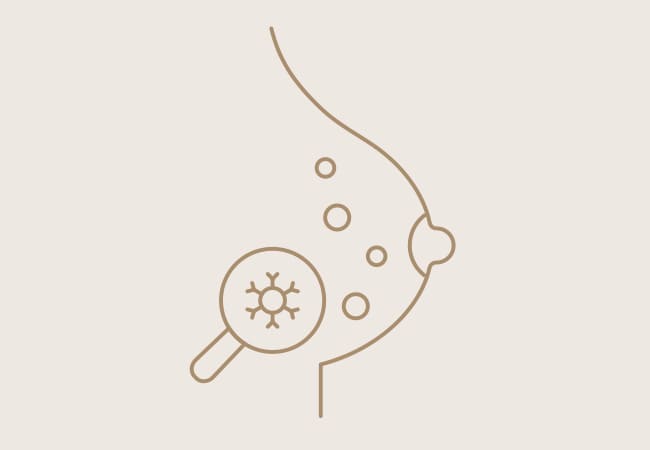
乳腺症
女性の乳房はその大きさ、形、硬さなど、1人ひとり異なり、そして変化しています。乳腺は女性ホルモンの影響を受け、月経周期だけでなく、成長や加齢に伴いその厚みや硬さが変わります。
治療は経過観察が基本となりますが、乳房痛の対症療法として、消炎鎮痛剤で一時的に疼痛管理を行うこともあります。
乳腺症の症状
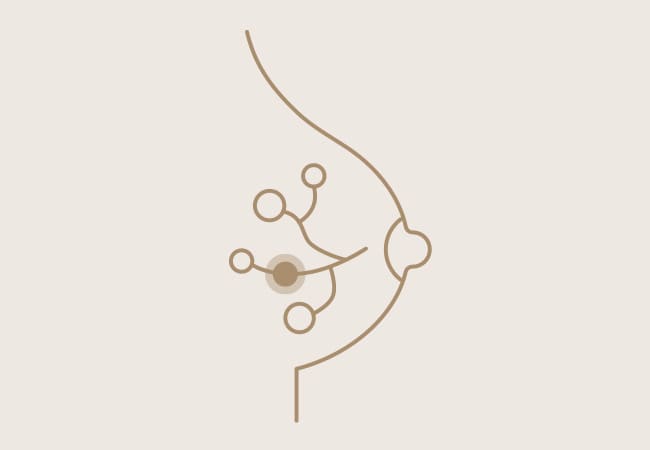
乳腺嚢胞(のうほう)
乳腺嚢胞は乳管の中に分泌物がたまり袋状になった状態をいいます。
エコー検査中に偶然に発見されたり場所や大きさによってはマンモグラフィで検出されることもあります。触るとしこりのように感じられることもありますが、症状がなく、乳がん検診の際に偶然発見されることが一般的です。
通常、分泌物は乳管を経て乳頭から排出されますが、何らかの原因(女性ホルモンの影響が関係)でその分泌物が乳管の中にたまってしまうと嚢胞が形成されます。
嚢胞の水分は増減を繰り返し、サイズが小さければ自然消失することもよくあります。
また、閉経期を過ぎれば縮小して、いずれ消失します。嚢胞の中身はただの液体成分で、良性であるため治療は必要ありませんが、嚢胞の中にがんが隠れていたり、がんと区別がつきにくかったりすることがあるため、検査が必要になることもあります。
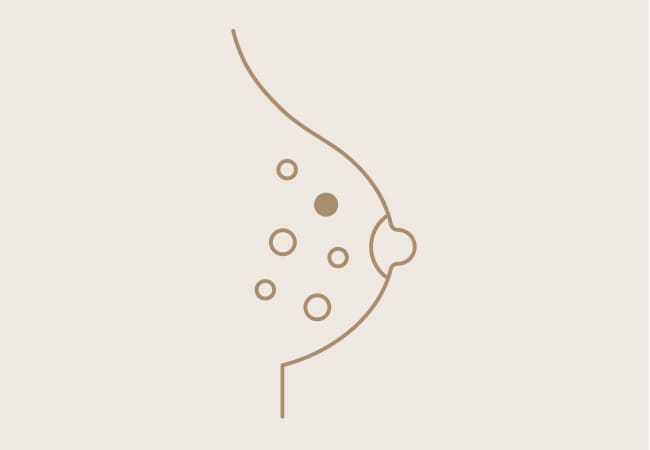
乳腺線維腺腫
10歳代後半から40歳代の閉経前の女性に多くみられる乳房の良性腫瘍です。
主な症状は乳房のしこりで、触ってみるとよく動きます。小さいものや柔らかいものだと乳がん検診で偶然発見されることもあります。
超音波検査などの画像検査や針生検で線維腺腫と診断がつけば基本的に治療は不要です。
乳がん発症とあまり関係のない疾患です。女性ホルモンの影響を受けて大きくなることがあります。
大きさは通常2-3cm程度で止まり、長く経過すると石灰化したり形が崩れてきて(陳旧性繊維腺腫)、経過とともに目立たなくなるケースもあります。
ただし、3cmを超える場合は巨大になる可能性がありますので、摘出手術が勧められることもあります。
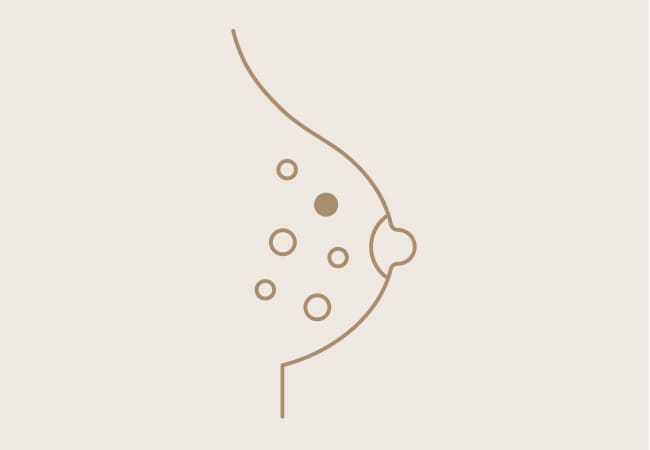
葉状腫瘍
乳腺に発生する比較的まれな腫瘍です。
組織学的に良性、境界型、悪性に分類されており、50%以上が良性で、約25%が悪性といわれています。
マンモグラフィ検査では、しこりが小さいうちは線維腺腫と同じような像を呈しますが、大きくなると分葉状となります。
葉状腫瘍と診断がついた場合、外科的切除を行います。
好発年齢は40歳代で、3cm以上の大きな腫瘤をみとめることが多く、良性であっても局所再発を起こすことがあります。
局所再発を繰り返すうちに悪性度が増すものもあるため注意が必要です。
悪性の場合、転移もしますので組織診(針生検)による診断をもとに個別の対応が必要となります。
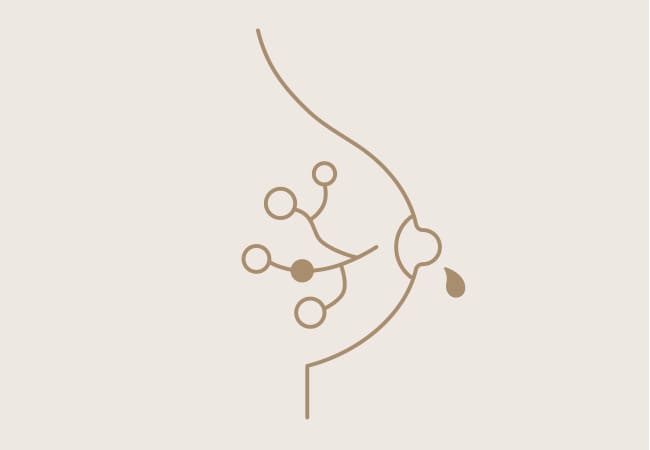
乳管内乳頭腫
30代後半から50代に多くみられる良性の腫瘍です。
症状としては乳頭から透明や薄黄色、血液が混じった赤や褐色の分泌物がみられます。
画像検査では非浸潤性乳管がん(のう胞内乳頭がん)と似ているため、鑑別に生検を必要とする場合があります。
乳管内乳頭腫は基本的に経過観察となりますが、血液の混じった分泌物が出続ける場合や検査で悪性の可能性が否定できない場合などは摘出手術が必要になることもあります。
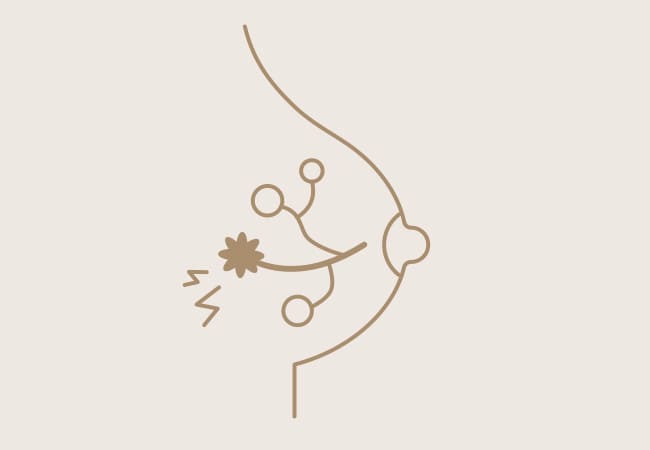
乳腺炎
乳腺に母乳がたまったり詰まったりするうっ滞(滞り)や、細菌感染によって起こる乳房の炎症です。授乳とは関係なく発症する場合もあります。
乳房のしこりや皮膚の発赤、痛みなどがみられ、細菌が侵入すると、化膿性乳腺炎となり、うみが出るようになります。
熱感を伴い、全身の症状として、発熱、悪寒、関節痛、頭痛、腋のリンパ節の腫れなどがみられることもあります。
化膿性乳腺炎の場合、症状を改善させるために、皮膚を切開してうみを出しやすくする処置が行われることがあります。
乳腺炎の症状
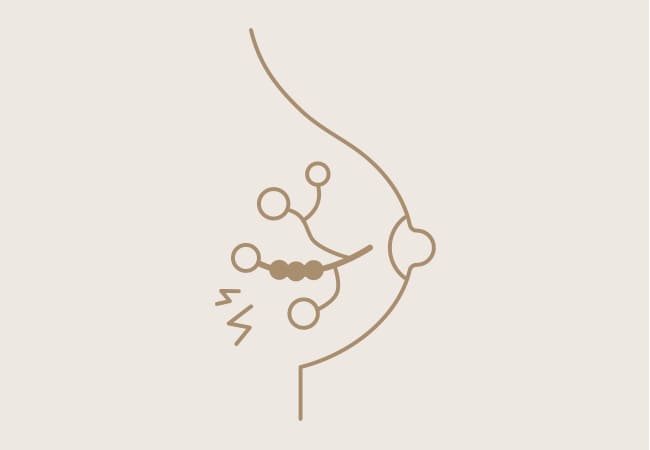
乳腺膿瘍(乳輪下膿瘍)
乳腺膿瘍は、化膿性乳腺炎が悪化して乳腺内に膿が溜まった状態のことです。
乳腺膿瘍の主な原因は細菌感染ですが、喫煙が関与するとも言われています。
乳腺膿瘍の症状は、化膿性乳腺炎とほぼ同じですが、より症状が強く、乳頭から膿が出ることもあります。
乳腺膿瘍の治療は抗生剤の内服です。
膿が多い場合や症状が改善しない場合は、針を用いて膿を排出する処置を行ったり、重症の場合は外科的な切開排膿が必要になります。
TOP